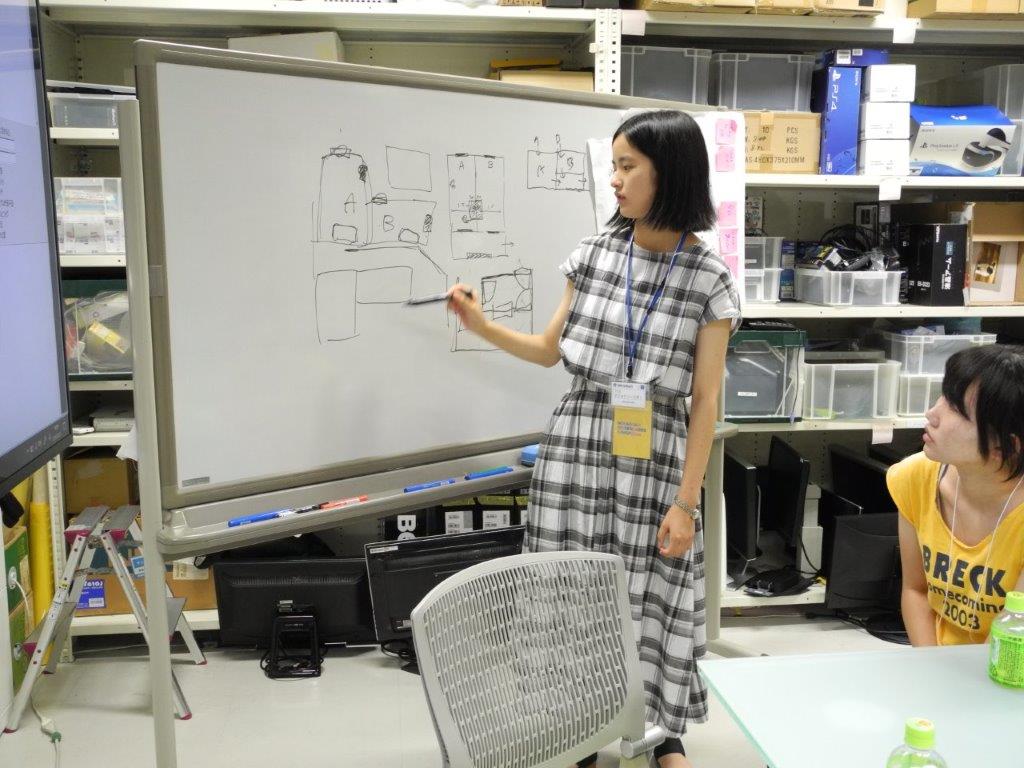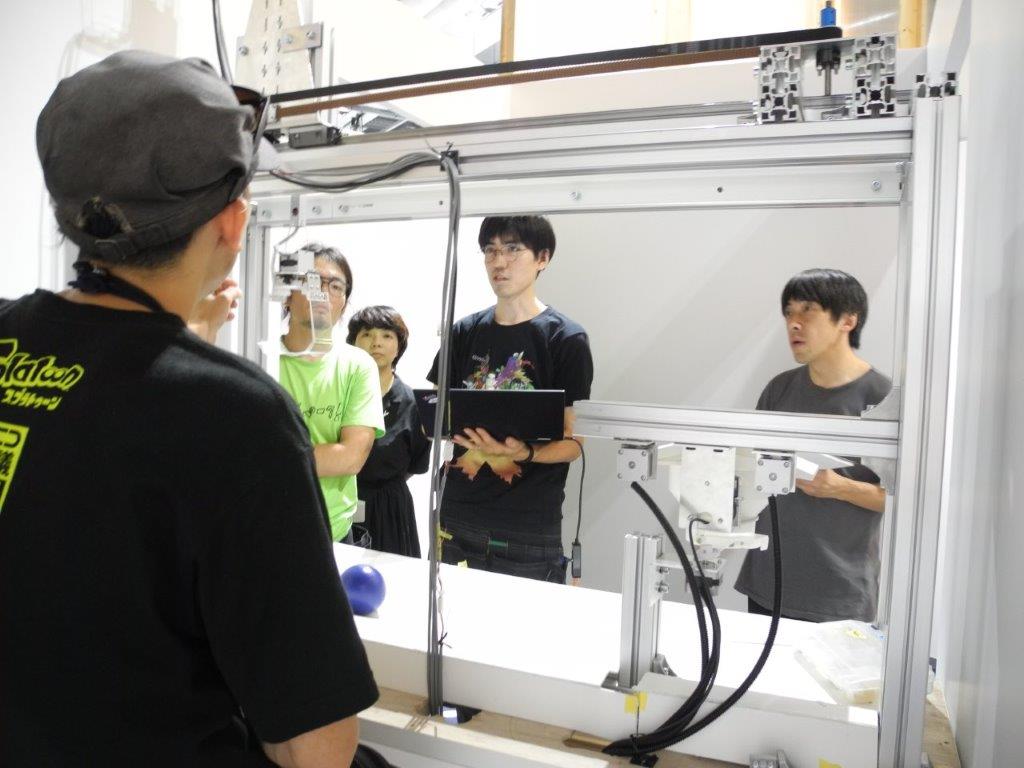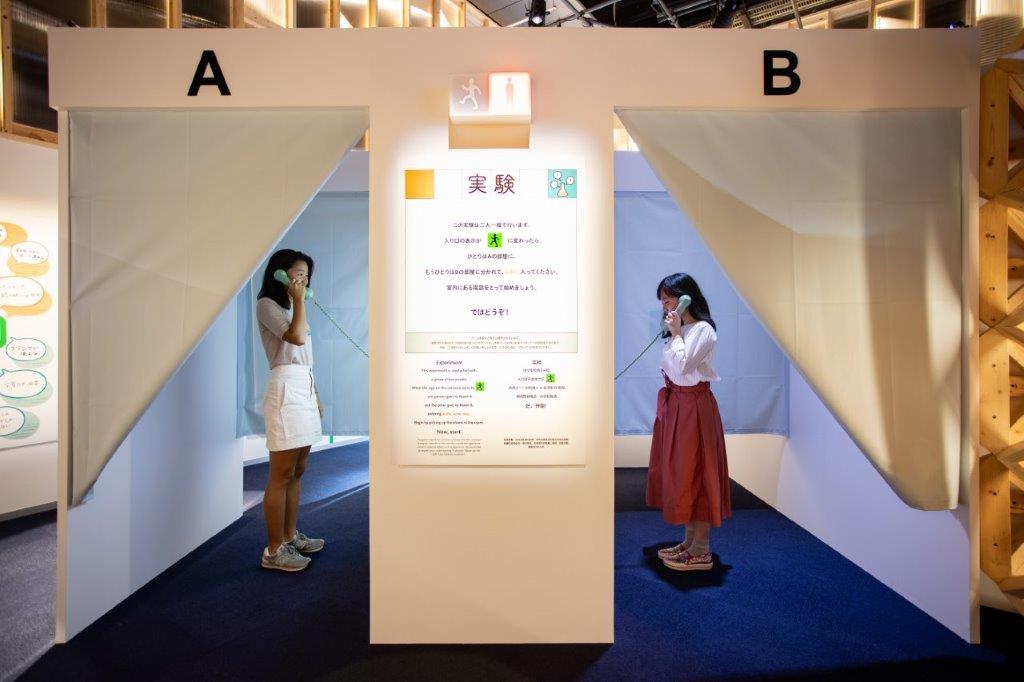展示概要
記念すべき第1期ビジョナリーラボでは、一般の15~26歳の若者をビジョナリーとして迎え、彼らのビジョンとアイデアを展示しました。
事前に行われたアイデアワークショップでは、全国から集まった参加者が、未来のコミュニケーションやテクノロジーについて議論し、発表を行いました。そこで優秀賞を受賞した3チームが、研究者・クリエイターからの助言を受けながら、クリエイターと一緒にアイデアを形にしました。その成果を展示するとともに、来館者自身もビジョンを描くためのヒントを紹介しています。
展示構成
STEP1 2030年をさぐる


2030年、そのとき社会はどんなふうに変わっていてほしいですか?ビジョンを描くとき、まずは現在を理解することが一つのヒントになります。ここでは未来を見通す手がかりになりそうな最先端のデータや事例を7つ紹介しています。
- 1. 「当たり前って、何ですか?」
テーマ:価値観の違い - 2. 「仕事もしたいけど、母でもありたい!」
テーマ:女性の労働 - 3. 「いいね!ほしい病なんです」
テーマ:承認欲求・SNS利用 - 4. 「彼氏と彼氏、ダメですか?」
テーマ:同性愛・同性婚 - 5. 「また天引きかよ~」
テーマ:高齢化社会・政治参加 - 6. 「田舎でも今の仕事、できますか?」
テーマ:地方の過疎化・テレワーク - 7. 「おばあちゃんでも、自分らしく」
テーマ:高齢者のQOL
STEP2 コミュニケーションをさぐる

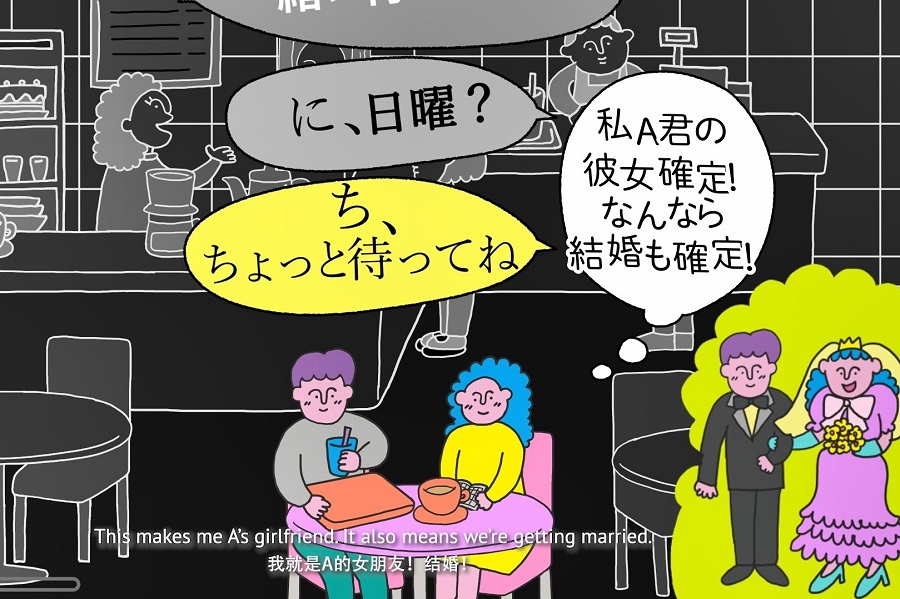
ビジョンのテーマは「2030年のコミュニケーション」。ここでは、あらためて「人と人の間で起こるコミュニケーション」を振り返ります。科学技術の発展により電話、メール、SNSなどのコミュニケーションメディアは大きく変わり続けています。それにより私たちのコミュニケーションスタイルはどのような影響を受けたのか考えます。
STEP3 ビジョンをさぐる
2019年3月に開催した「未来館ビジョナリーキャンプ」。このワークショップで優秀賞を受賞したビジョナリーたちは、6ヶ月間でビジョンを目に見えるかたちへとつくりあげました。科学の知見を提供する研究者と、ビジョナリーと共にビジョンを具現化するクリエイターたち。彼らをメンターとして3チームが挑戦し、成果を展示しました。
1. チーム家族 「MEDERU」
ビジョン:物理的距離を超えて家族のきずなを保つ
2. チーム葛藤 「Life Assistance Store」
ビジョン:テクノロジーを使うときに生まれる葛藤を大事にする
3. チームパー 「心ノ齟齬ノ実験室」
ビジョン:コミュニケーションの「不完全さ」を受け入れる
エピローグ ビジョナリーキャンプをあとにする前に…


同じテーマでも、描くビジョンは多種多様。ワークショップに参加した他のチームのビジョンを見てさらに考えを深めます。
最後に、「ビジョンにどう関わりたいのか」自分自身に問いかけてみましょう。そして、あなたの意見に最も近い「宣言テープ」を胸に貼って、ビジョナリーキャンプをあとにします。
プロジェクトの様子
基本情報
- タイトル
- ビジョナリーキャンプ
- 会期
- 2019年10月4日(金)〜 2021年2月1日(月)
- クレジット
-
【企画プロデュース】 宮原裕美(日本科学未来館)、遠藤治郎(日本科学未来館)
【立案】 小澤淳(日本科学未来館)
【協賛】 ブルームバーグL.P.
【展示制作】
<監修>「Step2.コミュニケーションをさぐる」
渡邊淳司(NTTコミュニケーション科学基礎研究所)
<出展者>「Step3.ビジョンをさぐる」
ビジョナリー:
池本次朗、柏木梨佐、北村尚、杉山萌音、高橋はるか、滝口小向葵、千代田彩華、永末茉莉絵、中林彩乃
<メンター>
クリエイター・展示制作:
齋藤達也(Abacus)
パーフェクトロン(クワクボリョウタ、山口レイコ)
松山真也 (siro)
研究者:
南澤孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)
山口真美(中央大学文学部)
渡邊克巳(早稲田大学理工学術院)
メンター協力:
金沢創 (日本女子大学人間社会学部)
都地裕樹 (中央大学研究開発機構)
楊嘉楽 (中央大学研究開発機構)
<企画・制作> 宮原裕美、眞木まどか、山川栞(日本科学未来館)
<空間設計・技術監理> 遠藤治郎、大橋永治(日本科学未来館)
<制作管理> 羽田野佳子(日本科学未来館)
<アートディレクション/グラフィックデザイン> Asyl
<イラストレーション> 磯本あかり(Redfish)
<映像> 今福薫、DENBAK-FANO DESIGN、Yasu Fujinami (YzFilms)
<製作施工> つむら工芸、コスモスファクトリー
<技術施工> サイエンティフィックつくば
<ウェブサイト> COLSIS
【ワークショップ】
<企画・制作>宮原裕美、遠藤治郎、入川暁之、河野美月、長田純佳(日本科学未来館)
<企画アドバイス>塩瀬隆之(京都大学総合博物館)
<プロモーション> MU inc.
<ウェブサイト> version zero dot nine
<記録写真> 西田香織
<ワークショップ参加者>
飯沼愛菜、池本次朗、市川優人、伊藤有沙、遠藤良子、岡田実香、柏木梨佐、木島亮、北原可南子、北村尚、熊崎美優、黒肱奈乃子、小泉花音、小林日向子、小峰結、嶋崎大地、杉山萌音、高田こはる、高橋はるか、滝口小向葵、田中柚希、千代田彩華、永末茉莉絵、中林彩乃、野口智滉、濱崎麗奈、廣谷紗瑛子、本間悠暉、三島早希、美間亮太、牟田薫穂、武藤胡桃、八重樫和輝、山口呉羽、吉岡美涼、吉村日菜、吉元史
2019年10月時点