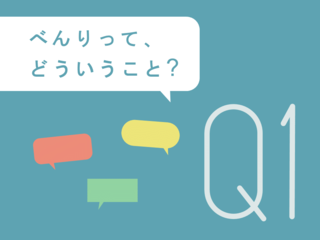
研究者に素朴な疑問をぶつけてみた!
YouTube Live
日々のふとした疑問を第一線で活躍する研究者たちとさぐります!
「こころって、どこにあるの?」、「いきているって、どういうこと?」。
だれもが一度は考えるけれど、そのまま忘れ去られることの多い素朴な疑問たち。未来館の「研究エリア」に所属する研究者といっしょに、一度立ち止まって考えてみませんか?
第一弾の問いは、「“べんり”って、どういうこと?」。
科学技術の進歩によって私たちの暮らしはどんどん“べんり”になっています。
たとえば、今では自宅にいながらオンラインで学校の授業を受けることも可能です。今後さらに科学技術が進めば、学校にわざわざ行く必要もなくなるかもしれません。みなさんは、それを“べんり”だと思いますか? みなさんがほしい“べんり”って、どんなものなのでしょう?
一方で、実験と探求をくりかえし、新しい技術の開発をめざしている研究者たちはどんな“べんり”を求めて、日々の研究をしているのでしょうか? 今回の疑問をいっしょに考えてくれるのは、専門分野の異なる3人の研究者です。軽くて長持ちする電池の研究を進める佐藤正春さんと、人混みで自由に動けるロボットを使って実証実験を行う坂東宜昭さん、そして音声を分析してより良いコミュニケーションをさぐる森勢将雅さん。
みなさんの考える“べんり”と、それぞれの研究者が考える“べんり”は、はたして同じ意味でしょうか?
視聴者のみなさんの声をひろいながら、素朴な疑問への考えを深める40分。まだ辞書にのっていない、新しい「べんり」の意味をいっしょにみつけませんか?
みなさんのご参加をお待ちしています!

1981年 東京農工大学大学院 工学研究科 工学化学専攻 修士課程修了、博士(工学)。企業において約20年間電池技術開発に従事した後、東京大学理学系研究科 特任研究員を経て、2020年よりスタートアップ企業を設立。未来の暮らしを変えるような、軽くてパワフルな次世代二次電池を開発中。現在は、ドローン用の電池開発を目指している。

2018年 京都大学 大学院情報学研究科 博士後期課程修了、博士 (情報学)。2018年より産業技術総合研究所 人工知能研究センター 研究員。自律移動ロボットを使って、たくさんの音が混じっている雑踏音環境から個別の音を取り出す研究に従事。定期的に未来館でロボット走行の実証実験に参加。
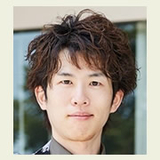
2008年 和歌山大学大学院 システム工学研究科 博士後期課程修了、博士(工学)。2019年より明治大学総合数理学部専任准教授。声によるさまざまな情報の発信と受信のメカニズムについて研究。2020年より「コミュニケーション・サイエンス」プロジェクト副代表。


未来館に併設されている「研究エリア」には、最先端の研究を進めるプロジェクトが常駐しています。一般の人々が研究に参画する場として今後さらなる展開を考えています。一緒に未来の研究をつくっていきましょう!
日本科学未来館 研究エリアについて