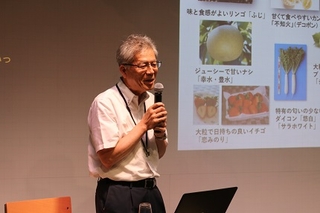
理想のイネを作るための地図づくり
「みどりの学術賞」関連イベント
スーパーやお米屋さんに行くと、価格や味、産地など、好みにあわせて様々な品種のお米を選ぶことができます。生産者から消費者まで多くの人が喜ぶ品種改良が今も盛んに行われています。
一方で、理想のお米の品種を作るためにはイネの特徴を数多く見極める必要があります。しかし、それらの特徴に関わる遺伝子の詳しい情報がよくわかっていない時代が長く続きました。熟練した研究員でも品種改良は難しく、一つの品種が誕生するまでに10年以上の年月がかかることも珍しくありませんでした。
こうした状況を変えようと、1991年、品種改良の土台となる「イネゲノム研究プログラム」がはじまりました。特徴にかかわるイネの遺伝子にはどのようなものがあり、それがどこにあるのか、といったイネ遺伝子情報の、いわば"地図"づくりです。
このプログラムに挑んだ研究者の一人が、今回みどりの学術賞を受賞された矢野昌裕先生です。当イベントでは、理想のお米への道案内となる「連鎖地図」と呼ばれるイネの遺伝子の地図と、その開発ストーリーについて、たっぷりご紹介していただきます。

1956年福岡県生まれ。九州大学を卒業後、同大学の大学院に進み、農学博士に。農林水産省農業研究センター(当時)に入り、以来ずっと国の研究機関で作物の品種改良などの研究に従事。2019年度より現職。文部科学大臣賞 研究功労者表彰、日本育種学会 学会賞、日本農学会日本農学賞、読売農学賞など受賞多数。
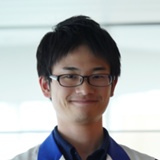
みどりの学術賞は、5月4日の「みどりの日」についての関心を促進し、植物、森林、自然環境などについて、国民の理解を深めることを目的に創設された学術賞です。国内において植物、森林、緑地、造園、自然保護などに係る研究、技術の開発その他"みどり"に関する学術上の顕著な功績のあった個人に内閣総理大臣から授与されます。
※主催者が当日撮影した写真やビデオを、日本科学未来館や内閣府等の記録や広報、また登壇者の論文執筆、学会発表などの目的で使用する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。