
地球上に暮らす私たちは、森林や海洋などの自然から多くの恵みを得て生きています。一方で自然は、地震や火山噴火、台風、豪雨など、時に大規模な災害を引き起こし、私たちにとって脅威となる存在でもあります。さまざまな表情を見せる自然に対して、私たちはどのように向き合っていけば良いのでしょうか?
地域の自然環境や防災などの探究活動に取り組んでいる、全国の高校生がオンラインでつながり、それぞれの活動を紹介し合い意見交換することを通じて、「恵みと災いをもたらす自然のなかで、どう生きるのか?」を考えるワークショップを開催します。第1部では、鹿児島県の沖永良部島在住の石田秀輝さんから、自然が教えてくれた心豊かな暮らしについてお話ししていただきます。つづく第2部では、参加高校生がいくつかのテーマごとの分科会に分かれ、専門家・実務家もコメンテーターとして加わりながら、意見交換を行います。“なかなかうまくいかないのだけれども良いアイデアない?”、“こんな活動したいけどどう思う?”など、探究活動における悩みや目標を共有しながら、新しい発見を目指して議論し合いましょう!
本ワークショップに参加する高校生を募集します。オンラインなので、全国・全世界どこからでも参加できます!前回は、15都道府県から52名の高校生の参加がありました。参加希望の方は、下記の「お申し込みフォーム」からお申し込みください。
分科会テーマ概要
自然災害
日本に暮らす人々はこれまで、地震、火山噴火、津波、洪水、雪崩などの数々の自然の脅威に直面してきました。自然の恵みのもとで暮らすということは、自然のもたらすリスクとも共に生きていくことであるという一面がみえてきます。身近な自然をみつめながら、地域の人々の命を守る防災に取り組むみなさん、自然災害について探究活動をしているみなさん。みなさんの知恵、経験、知識を集めて、これからの自然災害との向き合い方を一緒に考えてみませんか?
地球環境・海洋環境
海、森林、干潟などの多様な景観、そして人間を含めたさまざまな生き物たちが暮らす地球。現在、この地球では気候変動や生物多様性の損失などが起こっています。身近な生き物の調査、自然の豊かさや危機について人々に伝える活動、現在の地球環境を取り巻く環境問題の解決を目指す活動などに取り組んでいるみなさん。地球環境の今とこれから、そして私たちができることについて一緒に考えてみませんか?
社会・伝承・歴史
2011年に発生した東日本大震災のような地震や津波だけでなく、火山噴火、ゲリラ豪雨による洪水や土砂崩れなど、日本にはこれまでにも多くの自然災害がありました。それらは、歴史書に記されているほど昔のものから、ご家族やみなさん自身が経験した最近のものまでさまざまです。今を生きる私たちは、これまでの経験や知見を、どのように次の世代へつなげることができるでしょうか?
※「伝承・歴史」分科会については、応募者の興味のテーマを反映し、「社会・伝承・歴史」と名称を変更しました。(2022年3月11日修正)
実施内容
オープニング
第1部 基調講演
石田秀輝 『自然が教えてくれた心豊かな暮らし方のか・た・ち』
第2部 テーマ別分科会
自然災害、地球環境・海洋環境、社会・伝承・歴史のいずれかのテーマの分科会に分かれて、議論を行います。ひとつの分科会は、高校生6~7人、専門家のコメンテーターと司会役のファシリテーターで構成されます。まず、高校生のみなさんにご自身の活動もしくは研究内容について2分程度で紹介していただき、その後、全員参加の議論に移ります。
第3部 全体共有とまとめ
各分科会から高校生1名およびコメンテーターより感想をいただきます。
クロージング
*プログラムと分科会は、一部変更する可能性がございます。
基調講演

石田 秀輝
地球村研究室 代表 / 東北大学 名誉教授
地球環境と経済活動が両立するためには何を考えなければならないのか、たどり着いたのが、自然のすごさを賢く活かす「ネイチャー・テクノロジー」という概念でした。そして、その上位の概念である「心豊かに生きる」を実践するために、沖永良部島に移住しました。
テーマ別分科会コメンテーター
社会・伝承・歴史

阪本 真由美
兵庫県立大学大学院 減災復興政策研究科 教授
防災を研究しています。もともとは国際政治を勉強していましたが、阪神・淡路大震災があり人生が変わりました。当時私は神戸大学の学生。海外にいたため、地震そのものは経験していませんが、同級生と同じ体験をしていないこと、当時何もできなかったことが、防災を志すきっかけになったと思います。
自然災害

植木 岳雪
帝京科学大学 教育人間科学部 教授
大学では山の地形の研究をし、その後高校教員を経て、大学院とつくばの研究所ではフィールドワークを基にした地形地質の研究をしました。昔の自然を調べて、これから起こる災害を予測し、被害軽減に役立てたいと思っています。

大場 玲子
名古屋市港防災センター センター長
名古屋市の防災教育施設で、自然災害への向き合い方を市民に伝える仕事を約10年しています。大学、大学院では自然科学を専攻。学生時代から地元の科学館で科学を伝え、日本科学未来館でも科学コミュニケーションに取り組んだことが今の仕事に繋がっています。
地球環境・海洋環境

鼎 信次郎
東京工業大学 未来社会DESIGN機構 Team Create / 環境・社会理工学院 教授
私が若い頃は、環境と名の付いた学科はほとんどなく、さてどの学科に行こうかなといった感じでした。最後はえいやと、河川についての分野があるとも知らず土木工学を選んだのですが、その学科名では表しきれないような様々な経験ができて、結果オーライでした。

蒲生 俊敬
東京大学 大気海洋研究所 名誉教授
大学時代は理学部化学科で学びましたが、大学院では海洋研究所に進学し、海で起こる様々な謎を解こうと、化学的な手法をもとに研究を続けてきました。地球表面の7割が海です。海でいま何が起こっているのか知ることが、地球環境を理解するうえで重要だと思います。

佐藤 哲
愛媛大学 SDGs推進室 特命教授/マラウイ統合資源管理プロジェクト代表
東アフリカの湖に潜って魚の生態の研究をしている中で、自分の研究が地域の人々にとって全く意味がないと気づいたあたりで、人生がおかしくなりました。紆余曲折を経て、今では地域のみなさんといっしょに持続可能な未来を創りあげるための、トランスディシプリナリー(超学際)研究を進めています。
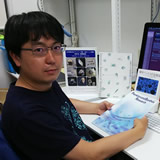
頼末 武史
兵庫県立大学自然・環境科学研究所 准教授/兵庫県立人と自然の博物館 主任研究員
海洋生物の幼生の研究がしたいと思い大学院に進学し、室内実験や遺伝子実験を行っていました。卒業後はしばらく大学の臨海研究施設に職を得て、野外実験や国際共同研究に従事。今後は室内外での調査・実験と国内外の研究者との連携によって、個性的な研究を進めていきたいと思っています。

北里 洋
東京海洋大学・デンマーク超深海研究所 研究員・上席研究フェロー
学生時代は地質古生物学を専攻して野山を歩き回り、大学院修了後は化石になった海洋生物(有孔虫類)の生理生態を明らかにする研究を行うようになり対象は海に。その結果、海陸問わず地質にも生物にも手を出す生物地球科学者になってしまいました。
企画・ファシリテーション

遠藤 幸子
日本科学未来館 科学コミュニケーター

大久保 明
日本科学未来館 科学コミュニケーター

大澤 康太郎
日本科学未来館 科学コミュニケーター

片岡 万柚子
日本科学未来館 科学コミュニケーター

清水 裕士
日本科学未来館 科学コミュニケーター
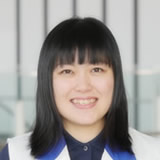
深津 美佐紀
日本科学未来館 科学コミュニケーター

若林 魁人
日本科学未来館 科学コミュニケーター
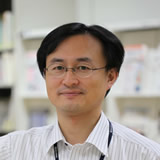
池辺 靖
日本科学未来館 科学コミュニケーション専門主任

谷村 優太
日本科学未来館 プラットフォーム運営室 室長代理
実施報告書

「高校生ちきゅうワークショップ2022 ~恵みと災いをもたらす自然のなかで、どう生きるのか?~」の実施報告書を公開します。石田秀樹さんによる基調講演の内容や、8つに分かれて実施した各分科会で語られたこと、ならびに各コメンテーターからのコメントをまとめています。
開催概要
- 開催日時
- 2022年3月26日(土)13:00~16:30
- 開催場所
- Zoom(Web会議システム)を使用します
- 対象
- 高校生
- 参加人数
- 80名(各分科会 6~7名程度)
- 参加費
- 無料
- 字幕の視聴について
-
字幕が必要な場合は、お申し込みフォームの備考欄にご記入ください。
ご対応方法については、参加決定後にご相談できればと思います。
- 参加方法
-
【事前申し込み制】
個人でも、学校のグループとしてでも参加可能です。グループで参加される場合は、グループ欄にグループ名(△部など)を、指導教員欄に活動をご指導されている先生のお名前のご記入ください。また、該当する指導教員の先生も、「教員用お申し込みフォーム」よりご登録をお願いいたします。
- 主催
- 日本科学未来館
- 協力
- 東京工業大学 未来社会DESIGN機構(DLab)
- お問い合わせ先
-
日本科学未来館
Tel: 03-3570-9151(開館日の10:00~17:00)
お問い合わせフォーム
