皆の未来に役立つ空間情報科学を求め、
博士たちは6人の研究者に会いにいきました。
博士たちは6人の研究者に会いにいきました。
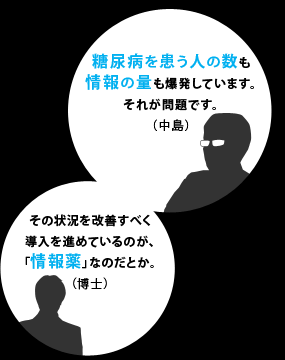
私は人の情報を"価値"に変える装置を開発しており、「シアワセ」が初号機だ。近い将来、超小型の生体センサーが完成した時のために、生体情報を健康に役立ててゆく方法を検討している。そんな時、生活習慣病の治療や予防に、生体情報を活用している研究者がいることを知り、彼が勤める大学病院に向かった。
2011年某日 九州大学病院にて
- 博士
- 先生は糖尿病がご専門とのことですが、糖尿病の世界では今、何が問題になっているでしょうか?
- 中島
- 2007年度の厚生労働省の統計調査によると、糖尿病を患う人の数は890万人です。今、その数が増加しているのですが、問題は増え方です。加速的に増えつづけているのです。医療がいくらがんばっても、増えてゆく患者さんを減らすことはできない。さらには1320万人もの糖尿病予備群といわれる人たちに対しても、医療は無力です。
- 博士
- 予備群を合わせると、国民の6人に1人ということですか。その数にも驚きなのですが、医療が無力というのはどういうことでしょう?
- 中島
- 糖尿病に関しては、そもそも行政が医療に期待していることと、医療が行えることには隔たりがあるのです。約500万人の患者さんは通院していますが、残りの400万人近くの患者さんは放置してしまっています。放置者はいずれ合併症を起こしてしまう可能性が高い。糖尿病はそれ自身ではなく、合併症に進展して重症になります。すると否応なしに医療を利用し始めるでしょうが、そうなれば莫大な国民医療費もかかってしまいます(*注1)。医療の対象は、病院に訪れてくる患者さんだけなんです。予備群の人たちも、発症しなければ医療の門はくぐらないでしょう。本来はできるだけ前段階で対処しなければいけない、つまり予防が重要なのに、今は事後対応でしかない。それが問題なんです。
- 博士
- 患者さんや予備群の人たちが自分の病気を放置してしまうのは、どうしてでしょう?
- 中島
- ガンや心疾患であれば、発症したらほとんどの人が診察を受けます。例えば、ガンは年間50万人が発症しますが、ほぼ全員が1度は専門医に診てもらいます。必死になりますからね。ところが糖尿病は発症しても、痛くも痒くもないため、放置しても大丈夫だろうと思われてしまう。しかしそれを続けたら、日本は破綻します。ただでさえ少子高齢化により労働人口が減っているのに、40代、50代の働き盛りの人まで合併症で奪われてしまったら、労働生産性は著しく落ちて、日本の社会は支えきれなくなるでしょうね。また、何よりも一番辛い思いをするのは患者さん自身なんです。
- *注1
- 莫大な国民医療費/厚生労働省が昨年発表した平成20年度の糖尿病の医療費は、総医療費34兆8084億円中、1兆893億円。前年比422億円の増加だった。糖尿病の増加及び国民医療費の増加は、国家財政の脅威となっている。
- 博士
- だからこそ予防医療が重要なのですね。糖尿病の治療や予防に、生体センサーを役立てることはできませんか?
- 中島
- とても期待できると思います。患者さんが通院する日は、日常ではなく、非日常の特別な日です。生活習慣病なので、"日常の生活"をとらえる必要があるのですが、しかし例えば、受診日前にだけがんばって節制して、受診後にラーメンを食べて帰る、というのはよくある話です。生体センサーは、その点、日常からの情報をリアルタイムに取ることができます。
また、通院時には患者さんから日常の状況をお聞きしますが、実はその中にはかなり真実でない飾りの部分が混ざってしまいます。例えば、運動はしていますか?と聞くと、先生の話をきいて頑張りました、と本人は話すのですが、実際は必ずしもそうではない。日本人はどうやら、「先生」とよばれる人を前にすると、ほめられたくなったり、指導通りにやっているように装う癖があるようですね。生体センサーはそうした虚偽を減らし、客観データを増やす効果があるのです。
- 博士
- なるほど。医療の現場に有効なんですね。
- 中島
- ただし、ひとつ大きな問題があります。それは、いわゆる「情報の爆発現象」が、医療の世界にも押し寄せていることです。つまり、情報過多が医療現場をダメにしているんですね。情報技術の進展によって、情報収集能力と共有能力が急激に上がったので、じゃあ医師と患者さんの情報共有を進めましょう、あるいは、データをグラフ化するなどして"見える化"しましょう、と短絡的に考えがちなんですね。でもそれは医者にとっては迷惑な話です。例えばある患者さんが家から心電図を24時間送りつづけたとしても、到底、医師が見きれるものではありません。データを受けた後の高次の情報処理は、現状、人間の頭に頼りきっている状態で、現場では完全にオーバーフローしています。処理できずに溢れた情報の責任を、医療者に押しつけている状態といえます。
- 博士
- 先生はそうした問題に対して、どのような解決策を考えていますか?
- 中島
- 爆発する情報を整理したうえで、患者さんに対して「適正なタイミングで適切な情報を提供する」ことが大切だと考えています。こうした情報は、一般の薬剤と同様に効果のある"薬"になりうると考え、「情報薬」とよんでいます。つまり、情報を"薬"として処方するのです。(*注2)
- *注2
- 情報薬/提唱者は、札幌医大の辰巳治之教授。
- 博士
- 情報薬は患者さんに対し、どのように処方されるのでしょうか?
- 中島
- 糖尿病は自覚症状が少ないこともあって、いかに意識を変えさせたり、行動を起こさせたりするかが大事なんですね。例えば、通院していても目に見えて効果を実感する病気ではないので、通院がイヤになり脱落する傾向が強いのですが、そんな時に「明日は受診予定日ですね」というメールが届くと、それだけでも効果があります。あるいは、「最近、体重を量っていませんね」と、患者さんの状態を確認する場合もあるでしょう。最近は加速度センサが発達してきたので、運動不足の患者さんがエレベータに乗った場合は「次は階段にしましょう」とアドバイスしたり、ちゃんと達成したらほめてあげることも可能になってきました。
- 博士
- そうした情報がタイミング良く届くことが重要なのですね。
- 中島
- 生体データをリアルタイムに近いタイミングで取得することで、危険な兆候を察知できますので、情報を提供して危険を回避させることができます。そのときに大事なのが、「適正なタイミング」と「適切な情報」です。また、そもそも運動不足であったり、体重測定をサボっていたりということは、他人に言われなくても本人が一番良く分かっています。いつ、どのような言い方をすれば相手の心に響くのか、という伝え方の工夫も重要です。ほめる場合もあれば、ときには強い調子で諌(いさ)めたほうがいい場合もあり、非常に人間的な対応が必要になるのです。
- 博士
- 情報薬は、どのように作られるのでしょうか?
- 中島
- 情報薬を医療の側で見れば、医療従事者への情報処理支援です。この仕組みを作ることが、情報爆発に対する解決策なのです。情報薬を作るにあたり、我々はまず、誰もが標準的な判断を行える医療上の設計図を作りました。いわば、医療を最短期間で行うプロセスを記述したマニュアルで、これを我々は「クリティカル・パス」とよんでいます。この言葉は臨界経路とも訳され、発電所のシステマチックな制御方法を取り入れています。クリティカル・パスを目安にすれば、医師でなくても行える領域の判断を医師にさせることなく、診察以前に医師以外の医療従事者が行えるようになります。
- 博士
- クリティカル・パスは、医療の効率を高めるツールのようですね。
- 中島
- 一方で、生活習慣病の治療には、ひとりひとり違った指導が必要です。ある一様な方法では一様な効果が望めないケースが多いのです。患者さんが申告する生活習慣と生体検査の結果のみからある情報薬を調合したとして、半分の人には有効でも、残りの人たちは、同じ情報薬のメッセージに対し、反発したり、怒り出す人までいる。性格や状況まで個別にプロファイリングして、どんな人がどんな情報薬を、どんな風に処方すると行動変容を起こしやすいか、という"知識"を積み重ねる必要があります。そこで求められるのが客観的な情報で、生体センサーが役立ちます。日常生活に伴って変化する身体状態のデータが貯まり、解析が進むことで、徐々に有効な処方のし方が見えてきます。「この人の場合はこの情報薬を出力してあげれば良い」という判断アルゴリズムの精度が上がっていくのです。その結果、患者さんは心地よく行動変容できるのです。
- 博士
- さらに、そうした知識の共有が、現在通院できてない患者さんや、予備群の人たちにも活かされていくわけですね。知識を見出すのに、我々工学者もお役に立てればと思います。

中島 直樹(なかしま なおき)
九州大学病院メディカル・インフォメーションセンター准教授、国際医療連携室長。国立情報学研究所客員准教授。1962年福岡生まれ。87年九州大学医学部卒業。97年医学博士。96-99年カリフォルニア大学サンディエゴ校研究員、2000年より九州大学病院に勤務。臨床活動の傍ら研究活動を行う。主な研究に、糖尿病疾病管理研究(カルナプロジェクト, 2003年~)、生体センサを用いた情報薬研究(情報大航海プロジェクトにおけるe-carna, 2008-09年度、および情報エネルギー生成基盤研究, 2010-13年度)、国際遠隔医療研究(アジア遠隔医療開発センター, 2003年度~)。


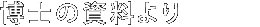
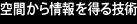

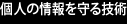
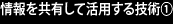
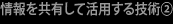
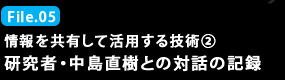

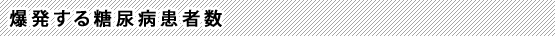
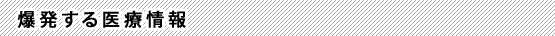
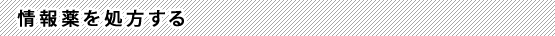
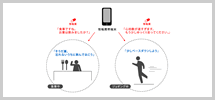
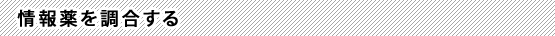
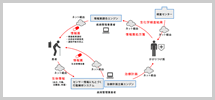
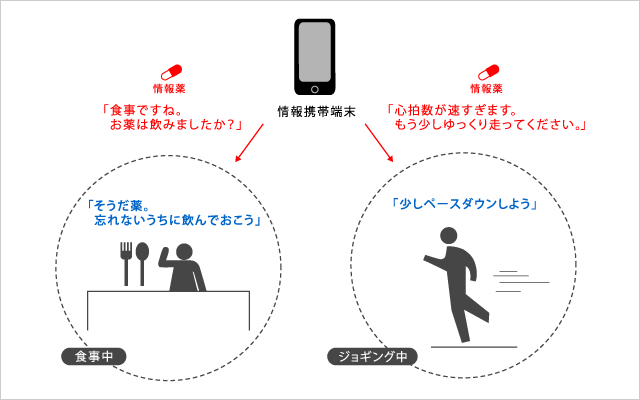 患者と情報薬のイメージ
患者と情報薬のイメージ
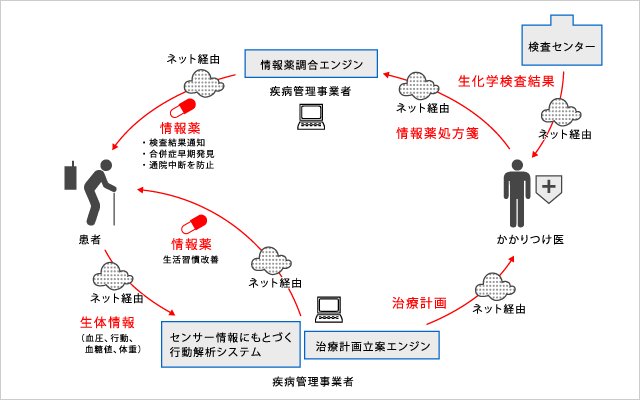 患者と医療関係者の間を循環する情報のイメージ
患者と医療関係者の間を循環する情報のイメージ

